サイト内の現在位置
土壌・地下水汚染調査
指定調査機関として土壌汚染対策法や地方自治体が定める条例に基づく土壌概況調査から土壌汚染対策工事のコンサルまで対応します。又、工業用水を利用するための地下水調査や、地下水汚染対策のための水理・水質調査、水質モニタリングの他、BCPのための水害に対する地下水シミュレーション解析サービスを提供します。
提供サービス
地歴調査(フェーズ1)
『地歴調査』とは、その土地の過去から現在までの土地利用状況を調査して、特定有害物質等による土壌汚染の可能性を評価する調査です。地歴調査の結果に基づき、使用履歴のある特定有害物質等による土壌汚染のおそれの区分を分類して、次の土壌調査のプランニングに反映させます。
地歴調査は、主に「土地利用履歴調査」と「有害物質使用履歴調査」に分けられます
- 土地利用履歴調査
登記簿謄本・公図、古地図・空中写真などの資料を収集して、昭和初期頃から現在までの土地所有者と土地利用の変遷について調査します。 - 有害物質履歴調査
ヒアリング調査や現地調査、行政への届出書類の確認を行い、事業活動において過去から現在までに使用や製造、保管、貯蔵された有害物質の種類や使用等の場所について調査します。
地歴調査によって、土壌汚染のおそれを3つ(土壌汚染のおそれが比較的多い・少ない・ない)に区分します。
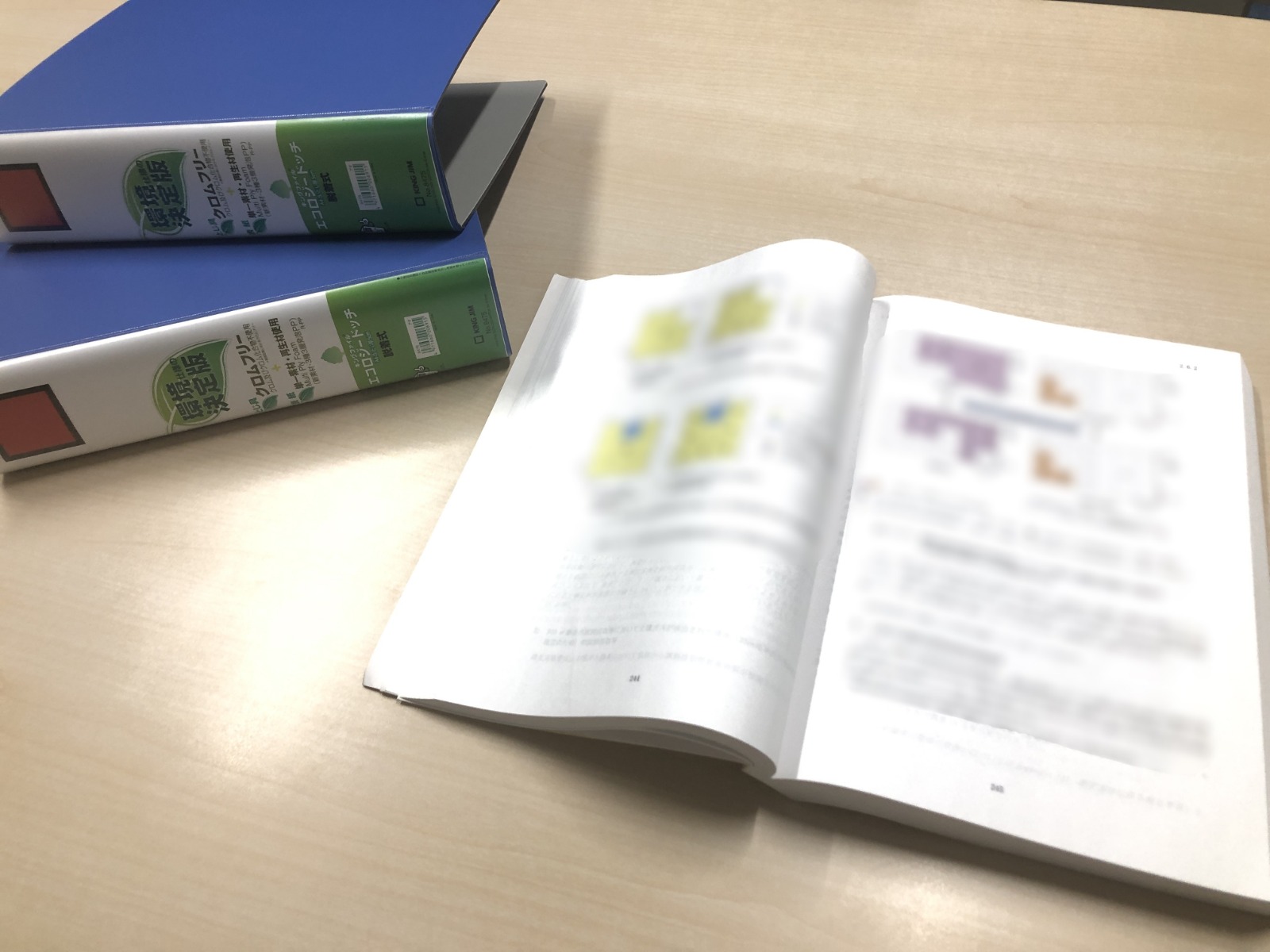
土壌汚染対策法において対象となる特定有害物質(汚染のおそれの評価対象)
- 第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物(VOC)12項目:クロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン等) - 第二種特定有害物質
(重金属9項目:カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素) - 第三種特定有害物質 (農薬5項目:シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN他))
上記の物質を含む製品を使用・保管している場合は、土壌調査(試料採取)が必要となる可能性があります。
土壌汚染状況調査(フェーズ2)

土壌汚染状況調査では、土壌汚染対策法に基づく調査や都道府県(政令市)の条例に基づき、土壌ガス採取や土壌採取を行い、汚染状況を評価します。
法律に基づく調査は、指定調査機関が行う必要があります。
当社は、指定調査機関として豊富な実績があります。
法や条例に基づく調査のほか、自主的に実施する調査にも対応します。
法第3条
水質汚濁防止法、下水道法における有害物質使用特定施設の使用を廃止した時(施設の廃止だけでなく、特定有害物質の使用をやめたときを含む。)に、土地の土地所有者等に、廃止の日から120日以内に、土壌汚染状況調査を行い知事へ報告する義務が生じます。
ただし、当該土地の場所が人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査の実施・報告の義務が一時的に免除されます(法第3条第1項のただし書き)。
法第3条第1項のただし書きの確認を受けた土地において900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合には、予め都道府県知事へ届出をする必要があります(法第3条第7項)。
法第4条
一定規模以上(3,000㎡以上)の土地の形質の変更を行う場合には、工事着手の30日前まで届出が必要です(法第4条第1項)。
法第4条では、盛土や掘削を問わず,土地の形質の変更の部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設のある工場又は事業場の敷地においては900平方メートル以上)となるものが届出の対象となります。
一定規模以上の土地の形質の変更届出を行う際に、土壌汚染状況調査結果報告を同時に行うことも可能です(法第4条第2項)。同時に調査結果を報告する場合には、土壌汚染状況調査の実施前に地歴調査結果報告及び調査計画、スケジュールについて所管の行政担当と協議しながら進めて行くことが大切です。
都道府県条例に基づく調査
都道府県(政令市)によっては、法より厳しい条例を制定し、土壌調査の契機を増やしている自治体もあります。
| 都道府県 | 条例 | 契機 |
|---|---|---|
| 東京都 | 東京都環境確保条例 (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例) |
3,000㎡ (法対象の場合900㎡)以上の敷地内での土地の改変を行う場合(法では形質変更面積が3,000㎡であるが、都条例では形質変更を行う土地の敷地面積が3,000㎡以上である場合に該当する点に注意が必要です。 |
| 神奈川県 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | H10年4月以降に特定有害物質の製造等を行う事業所について、形質変更の面積に関係なく調査が必要です。 |
| 滋賀県 | 滋賀県公害防止条例 | 土壌汚染対策法施行以前に廃止した特定施設があった場合、その敷地について形質変更の面積に関係なく調査が必要です。 |
土壌汚染対策コンサル
土壌汚染が顕在化した場合に、土壌汚染対策法や各地方自治体の条例に準拠した手続きをはじめ、最適な土壌汚染対策工法の提案、施工監修、お客様に寄り添ったコンサルティングサービスを提供しています。
主な土壌・地下水汚染対策工法の実績
掘削除去
汚染土壌範囲を重機や人力によって取り除く対策工法です。

原位置浄化(化学処理(還元分解))
攪拌混合機械を用い、汚染土壌中に鉄粉を注入しながら有機塩素化合物を還元分解する対策工法です。

原位置抽出(土壌ガス吸引・地下水揚水)
揮発性有機化合物によって汚染されたサイトにおいて複数の孔を設置し、土壌中から気体と液体を吸引することで、汚染を除去する対策工法です。


その他
原位置浄化(化学処理(酸化分解)、生物処理(バイオスティミュレーション))や高圧噴射置換法、透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止措置など、豊富な実績を有しています。
また、対策工事後のモニタリング業務も対応いたします。


地下水調査
工業用水を利用するための地下水調査や、地下水汚染対策のための水理・水質調査、水質モニタリングの他、BCPのための水害に対する地下水シミュレーション解析サービスを提供します。
地下水モニタリング
土壌汚染対策法では、原位置浄化による措置完了後、地下水汚染が生じない状況を2年間モニタリングする必要があります。また、お客様の自主的な環境マネジメントの一環として行われる定期的な地下水モニタリングにおいて、モニタリング計画の立案、分析データのトレンド整理など支援しています。
また、モニタリング結果に応じた地下水汚染調査・対策コンサルまで幅広くお客様の抱える問題解決に向けて取り組んでいます。
地下水汚染調査
有害物質の漏洩事故や過去の廃棄物埋立などに起因する地下水汚染について、汚染物質の種類と濃度、地下水帯水層の構造、地下水の流向・流速、汚染源と拡散メカニズム、汚染物質の到達距離の予測などを総合的に調査し、応急的な拡散防止から恒久的な地下水浄化対策までワンストップで対応しています。
地下水シミュレーション解析
近年、線状降水帯や台風がもたらす大雨による洪水の影響で工場の地下階の設備が故障する被害が心配されます。
当社では、降雨による河川水位の上昇と地盤中の地下水の連動をシミュレーション解析するサービスを提供しています。
また、親会社のNECファシリティーズとの協業により、シミュレーション解析結果に応じた設備の安全な高さへの移設・更新工事を提案することでお客様のBCP対策を支援しています。